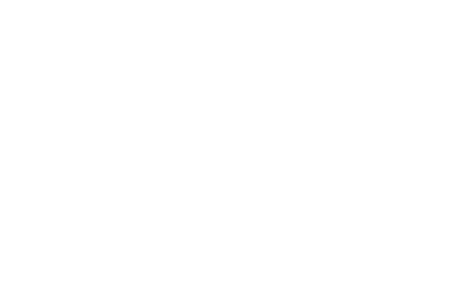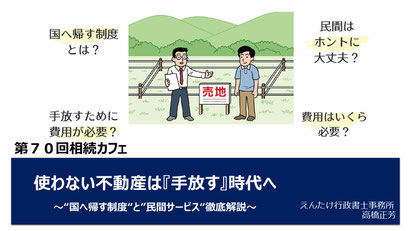
セミナー概要(2025年7月20日開催)
もくじ
1.なぜ今『手放す』時代なのか?
2.国へ帰す制度 相続土地国庫帰属制度
3.民間の引き取りサービス
4.その他の解決方法
【1.なぜ今『手放す』時代なのか?】
<ポイント>
使わない不動産を持っているだけで、様々なリスクが発生します。
●経済的リスク ⇒固定資産税、維持・修繕費、
●損害を与えるリスク ⇒近隣トラブル、損害賠償、犯罪
●精神的リスク ⇒不安、トラブルがあった時のストレス
●将来リスク ⇒不動産を持っているだけで、上記のリスクがつきまとう
【2.国へ帰す制度 相続土地国庫帰属制度】
<ポイント>
2023年4月27日にスタート。
相続によって取得した不要な土地を、国に引き取ってもらうことができます。
<どんな人が利用できる?>
相続や、相続人に対する遺贈で土地を取得した人が対象です。 売買や生前贈与で取得した人は直接利用できませんが、 相続で土地を共同所有している場合は、全員で申請すれば利用可能です。
<費用はどれくらい?>
申請時にはまず審査手数料として、土地1筆あたり14,000円が必要です。
そして、無事に審査を通過し、国に土地を引き取ってもらう際には、土地の管理費用10年分とされる負担金を納付します。
負担金は原則として20万円ですが、 宅地や農地、森林など、土地の種類や面積によっては、管理コストを反映して金額が変動します。
・宅地(市街化区域など)の例
100㎡の場合:約55万円、200㎡の場合:約80万円
・農地(農用地区域など)の例
1,000㎡の場合:約110万円
・森林の例
10,000㎡(1ヘクタール)の場合:約37万円
<注意!引き取ってもらえない土地とは?>
便利な制度ですが、どんな土地でも引き取ってもらえるわけではありません。国が管理するのに過大な費用や労力がかかる土地は、申請が却下されたり、不承認になったりします。
<主な却下・不承認の要件>
建物が建っている土地、担保権などが設定されている土地、境界が明らかでない、または所有権で争いがある土地、土壌汚染がある土地、崖や、管理を阻害するような工作物・樹木がある土地
他人の通行に使われている土地(通路など)
制度の詳細は法務省「相続土地国庫帰属制度」ホームページをご確認ください。
申請には、土地の図面や現地の写真など、多くの書類準備が必要です。 専門家のサポートも視野に入れると良いでしょう。
【3.民間の引き取りサービス】
国庫帰属制度の要件に合わない場合や、相続以外の理由で土地を手放したい場合に検討できるのが、民間の事業者による「引き取りサービス」です。
これは、所有者が事業者に処分費用を支払って、不動産を引き取ってもらうサービスです。
<費用や実績は?>
国土交通省の調査によると、引き取り料は数十万円から数百万円と幅広く、 近年その利用件数は増加傾向にあるようです。
弊事務所で関わった事例
・事例A:40年前に購入した山の麓の宅地 ⇒ 処分費用40万円
・事例B:山に囲まれた集落の倒壊した家屋のある宅地 ⇒ 処分費用100万円
・事例C:開発されると聞いて購入した手付かずの山林 ⇒ 処分費用70万円
<注意!悪質な業者も存在>
手軽に見える民間サービスですが、残念ながら悪質な業者が存在するのも事実です。負動産に詳しい弁護士も警鐘を鳴らしています。(弁護士 荒井達也 X(@AraiLawoffice)より)
悪質業者の典型的なパターン:
①高額な引き取り料だけ受け取り、名義変更をしない。
②本来なら売却できる価値のある不動産なのに、高額な引き取り料を請求する。
③名義変更だけして、後は管理せず放置する(結局、元所有者の責任問題に発展するリスク)。
④会社の経営が悪化し、倒産させてしまう。
業者を選ぶ際には、実績や契約内容を慎重に確認することが極めて重要です。
国土交通省の資料「不動産取引に係る新たなサービス形態について」も参考になります。
【4.その他の解決方法】
国や民間サービス以外の方法をご紹介します。
1. 相続放棄 ※親等が所有する不動産を引き継がない
・メリット: 土地だけでなく借金なども含め、一切の財産を引き継がなくて済む。
・デメリット: 現金や株など、必要な財産もすべて手放すことになる。 また、相続放棄をしても、次の管理者が決まるまで管理責任が残る場合があります。
2. 無償譲渡・廉価譲渡
隣人や知人など、土地を欲しがっている人に無償か安い価格で譲る方法です。
ただし、引き取り手を見つける必要があり、 農地の場合は法律上の制限もあります。
3. 売却
最も理想的な形ですが、買い手を見つけるハードルは無償譲渡よりもさらに高くなります。
4. 所有を続ける(手放す以外の方法)
「子どもに迷惑がかかるから」という思い込みで手放そうとしていませんか? 例えば、農地なら耕作を委託して賃料を得たり、 山林なら固定資産税がごくわずかで、所有者責任も限定的だったりすることもあります。 現実をよく知れば、考え方が変わるかもしれません。
【まとめ】
使わない不動産の問題は、もはや他人事ではありません。放置すればするほど、リスクと費用は膨らんでいきます。
今回ご紹介したように、不動産を手放すための選択肢は一つではありません。
・相続した土地で、建物がなく境界がはっきりしているなら「国庫帰属制度」。
・建物がある、相続以外の土地を手放したいなら「民間サービス」。
・親の不動産なら「相続放棄」。
・引き取り手が見つかりそうなら「譲渡」や「売却」。
まずはご自身の不動産がどのような状況にあるのかを正しく把握し、どの方法が最適なのかをじっくり検討することが大切です。お困りの際は、ぜひ一度、私たちのような専門家にご相談ください。